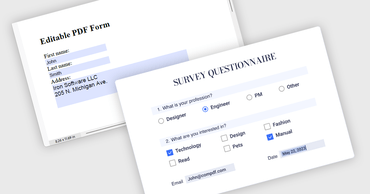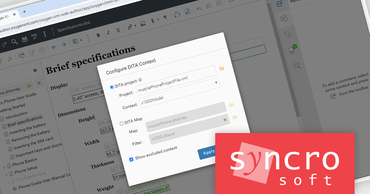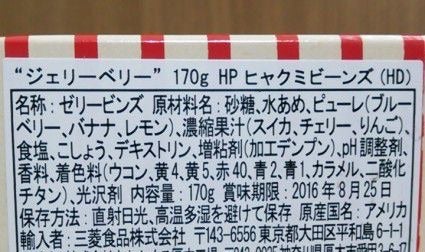『ヒア アフター』を渋谷シネパレスで見てきました。
(1)本作品を監督したクリント・イーストウッド監督の映画は、最近では『
インビクタス』や、『
チェンジリング』、『
グラン・トリノ』を見ているので、この映画も頗る楽しみでした。
本作品は死を巡るものといえますが、これまでのイーストウッド監督の作品も、むろん決して死を扱っていないわけではありません。『チェンジリング』は、幼児の大量誘拐殺人事件が関係していますし、『グラン・トリノ』でも、イーストウッド監督が演じるウォルトは銃弾を浴びて死んでしまいます。ですが、本作品のように死それ自体を真正面から取り上げている作品は、見当たらないのではと思います。
映画は、3つの都市で展開される死を巡る3つの物語で構成されているところ、ラスト近くになってから、それまで独立して展開されていたそれらの物語が微妙に絡まってきて、ラストのハッピーエンドにたどり着くというわけです。
ただ、これらの3つの物語は、同じく死を巡ると言っても次元が異なっています。
第1の物語では、パリの超売れっ子TVキャスターのセシル・ドゥ・フランスが、東南アジアのリゾート地で大津波に出遭って、あやうく死にそうになります。この物語では、彼女自身が死後の世界を体験することになります。
![]()
第2の物語では、サンフランシスコに住む霊能者のマット・デイモンの悲哀が描かれています。その能力を使うと、却って人が彼から離れていくのです。この物語では、死後の世界とのコミュニケーションが描かれています。
![]()
そして、第3の世界では、ロンドンの双子の兄弟の兄が交通事故で死亡し、残された弟がなんとか兄と接触したいと強く望みます。この物語では、直接霊魂は関係してきません。
![]()
このように、それぞれの物語は次元が微妙に異なっているため、そのままでは絡み合わないところ、セシル・ドゥ・フランスがパリに戻った後に著した著書(題名が『HereAfter』)が評判を呼び、ロンドンで開催されたブック・フェアで朗読したことから、3人が絡み合ってきます。
ここらあたりはご都合主義的な感じがしないわけではありませんが(注1)、実にうまく物語が展開していって、ラストに至って観客を幸福な感じにさせてしまいます。さすがはクリント・イーストウッドというべきでしょう(注2)。
ところで、死を巡る映画というと、なんといっても『おくりびと』(2008年)が思い出されますが、同作品はあくまでも納棺という儀式にかかわるものでした。また、死後の世界を描いた映画ならいくつか見つかることでしょう。たとえば、『丹波哲朗の大霊界』(1989年)はどうでしょうか(なお、最近見た『
きみがくれた未来』は、交通事故で死んだ弟と生き残った兄とのお話で、弟の幽霊が登場するものの、あくまでもこちら側の世界の話です)。
今回のイーストウッド監督の作品は、むしろ生と死の境目を巡って物語を作り上げたものといえるでしょう。死後の世界はどんなものなのかについて人は非常に興味を持っているところ、まともに取り扱えば際物的な映画になりかねないことを踏まえて、ギリギリのところで踏みとどまった感じです。
霊能者であるマット・デイモンが、依頼者の手を握って、彼岸の世界に踏み込みますが、バンと音がして一瞬間その世界が映像で描き出されるものの、そしてマット・デイモンは暫く死者の話を聞いたり話しかけたりしますが、死者の様子はそれ以上映像化されません。
津波に遭遇して溺死するところだったセシル・ドゥ・フランスも、息を吹き返す前、ホンの一瞬間だけ死後の世界を覗き見たような映像(いわゆる「臨死体験」というものでしょう)が映し出されます。
この映画で描かれる死後の世界は、どんな構造をしているのでしょうか?もちろん、明示的に映像化されているわけではなく実に短い時間しか見ることが出来ませんから、単なる推測にすぎません。
ただ、双子の兄弟の兄は、交通事故に遭ってからは、まだ死後の世界の入口にいるようです。暫くマット・デイモンと話をした後、別のところへ行くと言って消えてしまいますから。力のある霊能者といえども、最早コミュニケーションが取れない奥の世界があるというのでしょう。
そして、まだ入口にいる場合には、霊能者と交信できるばかりか、生前の世界に対しても一定程度の働きかけが可能なようです(注3)。
とはいえ、マット・デイモンが料理教室で知り合った女性の場合、彼は、まず母親の霊と話しますが、暫くすると父親の霊とも話すようになります。父親が亡くなったのはかなり以前のことでしょう。とすると、霊能者が交信できる霊魂は、いったいどのくらいの間、死後の世界の入口近くにさまよっていられるのでしょうか(注4)?
それに、マット・デイモンが依頼者の手を握って死後の世界と接触すると、依頼者に関係する霊魂が直ちにマット・デイモンに現れることからすると、彼らは、こちら側にいる人たちそれぞれの背後近くに常時存在しているとも考えられるところです(背後霊!)。
さて、この映画でも、俳優陣は、それぞれがなかなかいい味を出していると思います。
マット・デイモンは、他の俳優だったら胡散臭さを感じさせてしまう霊能者の役ながら、誠実な人柄が全体に滲み出ていて、観客に違和感をマッタク感じさせません。『インビクタス』の際のもその瑞々しい演技に目を瞠りましたが、今回もはまり役と言えそうです。
また、セシル・ドゥ・フランスは、これまで見たことはありませんが、売れっ子ニュースキャスターならば斯くあり何なんという感じで、生き生きと演じています。ベルギー出身とのことで、おそらく何カ国語も出来る国際俳優なのでしょう。
(2)この映画のセシル・ドゥ・フランスを巡る話は、いわゆる「臨死体験」に関するものと思われます。
例えば、評論家・立花隆氏の『臨死体験』(文春文庫)の「上」の冒頭では、臨死体験とは、「事故や病気などで死にかかった人が、九死に一生を得て意識を回復したときに語る、不思議なイメージ体験」とされています。
引き続いて、それらには、「三途の川を見た、お花畑の中を歩いた、魂が肉体から抜け出した、死んだ人に出会ったといった、一連の共通したパターンがある」とも記載されています(注5)。
さらに、「その意味付けと解釈を巡って、さまざまの議論がある」とし、次のような二つの対立する見方があると述べられています。
イ)「臨死体験は魂の存在とその死後存続を証明するもの」(注6)。
ロ)「臨死体験というのは、生の最終段階において弱り切った脳の中で起こる特異な幻覚にすぎない」(注7)。
立花隆氏は、同著「下」の末尾の方で、「私も基本的には脳内現象説(上記のロ)が正しいだろうと思っているものの、もしかしたら現実体験説(上記のイ)が正しいのかもしれないと、そちらの説にも心を閉ざさずにいる」(P.474)としつつも、「ただ、実を言うと、私自身としては、どちらの説が正しくても、大した問題ではないと思っている」と言っています。
なぜなら、「死にゆくプロセスというのは、これま考えていたより、はるかに楽な気持ちで通過できるプロセスらしいということがわかってきたから」、「そして、そのプロセスを通過した先がどうなっているか。現実体験説のいうようにその先に素晴らしい死後の世界があるというなら、もちろんそれはそれで結構な話である。しかし、脳内現象説の言うように、その先がいっさい無に成り、自己が完全に消滅してしまうというのも、それはそれでさっぱりしていいなと思っている」と続けています。
もしかしたら、イーストウッド監督がこの映画で問題提起しているようなことは、実は余り問題にならないのかも知れません。
なおかつ、このブログの前の
記事で取り上げた荒川修作氏が言うように、「天命を反転」して「死なない子供」になるのなら(注8)!
(3)
渡まち子氏は、「生と死を明確に分離するのではなく、私たちの周辺に当然あるものとしての死を、肯定的に受け入れる。そのことをスピリチュアルな体験を通して描くスタイルは、リアルな人間ドラマを得意とするイーストウッドの新しい挑戦なのだ。1930年生まれの老巨匠は、映画に対して果敢なチャレンジ精神を決して忘れない」として65点をつけています。
前田有一氏も、「それにしてもクリント・イーストウッド監督はすごい。丹波哲郎も仰天の「死んだらこうなった」を描きながら、これだけ良質な、まともな大人が真剣にみられるドラマに仕立てるのだから」などとして70点をつけています。
また、映画評論家・秋山登氏は、2月25日の朝日新聞夕刊で、「イーストウッド演出はまことにリアルだ。……それでいて、語り口は、律儀で、抑制が利いていて、品がある。80歳の大家の風格がおのずとにじみ出ている。/ただし、知的な遊びではなく、正面から死後を見すえようという心意気は買うけれど、……底の浅さは隠せない」などと述べています。
(注1)一介の工場労働者にすぎないマット・デイモンが、チャールズ・ディケンズの熱烈な愛好者で、ロンドンのバス・ツアーに乗り込んでディケンズの家(博物館)を訪ねたり、ブック・フェアで開催された『リトル・ドリット』の朗読会に参加したりするなどは、あまり常識的ではない感じがしますし、セシル・ドゥ・フランスは、その著書の評判がいいからと言って、同じようにブック・フェアですぐに朗読会を持てるのかなと思います。さらに、双子の兄弟の弟の方は、それほど本好きのようにはみえないにもかかわらず、ブック・フェアの会場をよくわかったように歩きまわります。
むろん大した疑問点ではありませんから、それほど気にならずに映画を見終わることは出来ますが。
(注2)とはいえ、実のところ、マット・デイモンは、霊能力者であるゆえに直前に恋人を失ったばかりですし、またセシル・ドゥ・フランスも、研究所の研究員から資料を沢山渡されるものの、特別な分析能力を持っているわけではないのですから、今後どうやって「死後の世界」と付き合っていくのか甚だ心許ない感じがします。さらに双子の兄弟の弟の方も、薬物依存症の母親を抱えて大変な生活が将来に控えています。それやこれやを考え合わせると、果たしてハッピーエンドとばかり言えるかどうか、かなり怪しい感じはしますが。
(注3)双子の兄弟の兄は、弟が乗ろうとしている地下鉄がテロに遭うことを察知すると、弟が被っていた帽子を吹き飛ばして、ちょうど駅に入ってきた電車に弟が乗り込めないようにします。その直後に、その電車で爆弾が爆発しますから、弟は死を逃れたことになります。
しかし、そうだとすると、生前の世界と死後の世界とが入り混じっていることになり、兄は亡霊的な存在といえ、むしろ『きみがくれた世界』のシチュエーションではないかと思います(そこでは、亡霊となった弟と生きている兄とが、森の中でキャッチボールをするのですから!)。
(注4)幼かった時分に悪いことをしてしまったと父親が料理教室の女性に対して謝っているところからすると、生前の世界に恨みがあったり言い残したことがあれば、死後の世界の入口近くにいつまでも居続ける(さまよう)ことができるのかもしれません。
それにしても、恋人と思っていた相手(マット・デイモン)から、自分の幼児期のトラウマを暴露されてしまったら、やはり逃げ出さずにはいられないでしょう!
(注5)ミュージシャンの桑田佳祐が、昨年の食道癌手術から復帰し、2月23日にリリースしたアルバム「MUSICMAN」には、「銀河の星屑」という曲が収録されているところ、その歌詞には“死後の世界”が描かれている感じです(
PVも、そんな感じが漂っています)。
たとえば、歌詞には、つぎのような下りが見受けられます。
「森を抜けると蓮の御池があってさ」
「水面に浮かぶ花を見て眩暈がしたよ」
「美しい女性(ひと)は微笑み手招きしている」
「痛みも苦しみも無い世界」
「何処かで母が呼ぶ声がする」
「なんてSpiritual」
なお、このことは、2月26日に放映されたNHKTV「復活!桑田佳祐ドキュメント〜55歳の夜明け」で知りました(『銀河の星屑』は、1月11日からスタートしたフジテレビ系火曜9時ドラマ『CONTROL〜犯罪心理捜査〜』〔主演:松下奈緒〕の主題歌)。
(注6)臨死体験に関する事例については、立花隆氏の著書にもイロイロ掲載されていますが、
このサイトでも取り上げられています。
(注7)事例としては、評論家の吉本隆明氏のものが典型的でしょう。
たとえば、辺見庸氏との対談集『夜と女と毛沢東』(光文社文庫)で、1996年8月に海で溺れかけたときのことについて、「よく臨死体験なんていいますけど、そういう色鮮やかな、ロマンティックな経験じゃ全然ないんです。……とにかく、ふっと意識がなくなって、ふっと目が覚めただけなんです。……目が覚めて、一体何だと思ったら、もう病院の部屋にいたというだけなんですね」と語っています(P.183〜P.184)。
(注8)「天命反転」、あるいは「宿命反転」とは、「不可能だと思われていることを留保し、留保された位置から、可能性の広がりを考察すること」であり、「たとえば、これまで人間は、必ず死ぬものだと思われてきており、また事実死んできたが、ひょっとして人間は死なないのだということまで予定に入れることができれば、これまでの通念ととは異なる範囲で、可能性の幅、あるいは選択肢を考えざるをえなくなる」のであり、「かりに人間の経験の可能性に向けて、無限の試みが続けば、すでに宿命反転は現実化の段階に入っている」。
(荒川修作+マドリン・ギンズ著『建築する身体』〔春秋社、2004年〕に付けられた「基本用語解説」〔訳者・河本英夫氏による〕から)
★★★☆☆
象のロケット:ヒア アフター
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()